令和7年 5月の法話
人権
生まれながらに人間が持っている、
尊厳・自由・平等などに関する権利を、
一般に「人権」といいます。
今、私達の社会の中では、不当に侵害され、
抑圧、差別を受けている人達がいます。
人権は、人間が幸せに生きることの権利であり、
それを回復するあるいは確立をはかることが願われます。
曹洞宗は、現在あらゆる差別の解消と人権啓発の活動に
真摯に取り組みを重ねています。
人権において、私達は常に、
差別しない・させない・許さないという
基本姿勢を持つことが求められています。
人がよりよく生きていこうとする生き方を、
誰も妨げることはできません。
分権や先入観、固定観念は打倒しなければなりません。
私達は自らの人権意識を深めながら、
事実を知る・考える・行動する人になりましょう。
随昌院からのお知らせ
当随昌院では、本堂、客殿を利用して、通夜・葬儀を営むことができます。
| 通夜よりの本堂客殿使用料 | 檀家 10,000円 | 檀家以外の方 50,000円 |
| 祭壇等利用料 | 檀家 5,000円 | 檀家以外の方 10,000円 |
*葬儀社や仕出し業者等の指定はありません。
*上記費用には、ご葬儀のお布施、戒名料等は含まれておりません。

新しくできた祭殿

新しくできた客殿

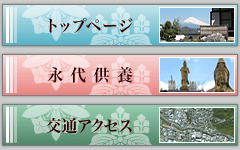

 随昌院 mobile site
随昌院 mobile site